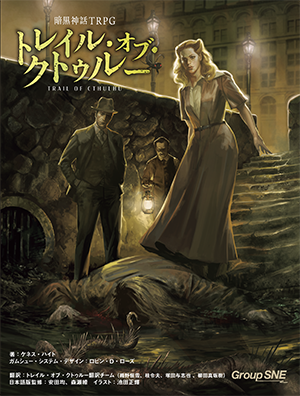【TRPGのスタンダードはもはやクトゥルフ】
新クトゥルフ神話TRPGを買ってからだいぶ経ちましたが、結局5,6回しか遊んでいない状態の星野☆船長です。
今回は、買ったばかりの暗黒神話TRPGトレイル・オブ・クトゥルーを紹介します。アイキャッチ画像はグループSNEのサイトから引用しております。
目次
基本情報
| 人数 | 2-6人くらい (キーパー含む) |
| 時間 | 120分~ |
| 発売 | 2020年 |
| 言語依存度 | 日本語版を買いましょう |
| ルールの複雑さ | CoCより読みやすく、簡単 |
| 遊ぶならどんな時? | 既存のCoCはやりつくした、またはルールブックを読んで断念した人にオススメ |
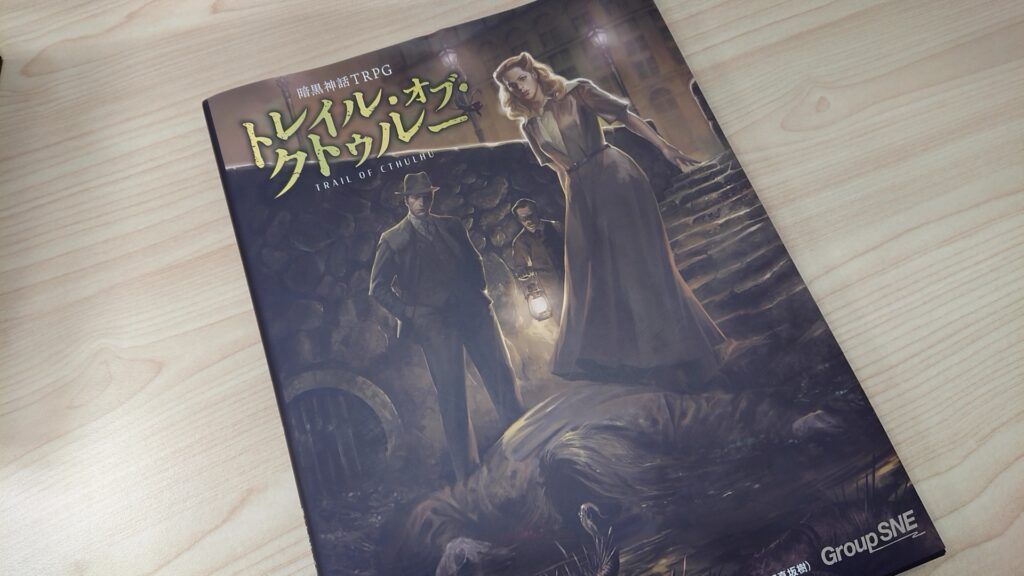
何故、紹介したいのか
まず、新クトゥルフ神話TRPGを5,6回でやめてしまった理由をお話すると、「決定的な手がかり」を些細な判定ミスで逃す→判定の振り直しでしくじって終わり……CoCのシステムで遊ぶとよく起きてしまう事ですが、この不遇があるからです。そういう事もあるよとは思うのですが、ダイス運でシナリオのバッドエンドに走り出してしまう、システム的に直面しやすいように思うのです。
もちろん反対もあって、いいタイミングで最高のダイス目を引くよね!と笑える時もありますがバッドエンドに向かった時、いい気持ちで狂気を楽しめる人達ばかりではありません。クリアしたかった、恐怖に打ち勝つエンディングであるべきだった。
これが普通だと思います。え?マスタリングの仕方が悪い?確かに船長のマスタリングは上手いわけではないです……
でも、ダイス目に不正は出来ないし、狂気に陥ってしまうルールを反故にしてまで生き残って、それがクトゥルフ神話に触れている者なのか?という気持ちもあります。
せめてオープンダイスでなければなぁ……じゃあ重要な手がかりの配置を修正して……あれ?また失敗!?なんて事も。船長がやりたいのは、そういうドタバタじゃあないんですよ!
正常と狂気の間のギリギリをくぐって、どうしようもない神や化け物連中から逃げたり封印したりする、謎解きを楽しんでもらいたいんです。
なので、今までと違うシステムでクトゥルフ神話の世界を冒険が出来たらいいのに……と思っていたところ去年の12月にこんな物が出ていたので、今日はもう紹介したくてしたくて……時間の余った時には読んで紹介しなくては!と思ったわけです。
CoCについて、なんだかマイナス要素をちょこちょこ書きましたが、決してつまらないと言いたいのではないです。旧版も含めればもっと回数やってますし、嫌いなら1,2回で辞めて他のシステムで遊んでるはずです。
別なシステムでクトゥルフ神話の恐怖を演出したいと感じている、もう既存のシナリオは全部遊んでしまった等、一番遊ばれているTRPGならではの問題を解決する、別なシステムとして、トレイル・オブ・クトゥルーは最適だと思います。
他に答えがあるとすれば、ゴーストハンターTRPGの再復活に期待するしかないな!と、グループSNE好きなのでちょっと思ったりもします。
トレイル・オブ・クトゥルーの紹介

ガムシューシステム
トレイル・オブ・クトゥルー(以下、ToC)ではガムシューシステムという調査や探索を楽しむシステムが使用されています。
ちょっと検索した感じでは、ToC以外でガムシューシステムを使った日本語のTRPGは見当たりませんでした。
元々が海外のシステムだからでしょうね。今回の輸入でみんなが楽しいと思えば、もしかしたら他のテーマの物も入ってくるのかも?英語では他にも色々出ているようです。
ガムシューとは元々ゴム底靴の意味で、転じてガムを踏むくらい様々な場所を足で調査する刑事を意味しています。つまり、探索や推理に重きをおいたシステムなんですね。
能力値が存在せず、技能にポイントを割り振ってキャラ作成をしていきます。割り振れるポイントはプレイ人数に応じて変化します。
技能さえ持っていればシナリオを進める為の手がかりは必ず入手出来るので、先に書いたシステム的な事故が起きません。
ダイスも6面体しか使わない
CoCを始めるにあたって、おそらくオフラインで遊んでいる皆さんは普段見慣れない20面や12面、4面のダイスを購入したと思います(CoCが遊べるようにセットで販売されている事もよくありますね)
でも、そのシステム自体が他のシステムと違い、ややこしさや大味さを作ってもいるのです。あんなにいろんな種類のダイスを使うTRPGなんて、他にはD&Dしか思いつかないです(あれ?超メジャータイトルだぞ!?)

でも、推理や探索の面白さを突き詰めるとするとD&Dのシステムでも事故ります。
やっぱり楽しみ方を変えるならシステム自体を変更しなければならないのです(そういえば、昔のD&Dは魔術師のHP低すぎて一撃で死ぬなんて事もあったなぁ。リアルかもしれないけど、それで死ぬ側はたまったもんじゃない)
100均で6面体のサイコロ買うだけで、とりあえず準備完了!という気軽さは良いと思います。
様々なファンに対応する2つのモード
クトゥルフ神話といえば、宇宙の彼方にいる邪神や旧支配者などの、人間にはどうしようもない連中が出てくる物です。
見ただけで発狂という、想像しづらい恐怖(見られたら石になると言われた方がまだわかりやすい)によって、人間が生物の頂点ではないという、あるいは当たり前の事実を突きつけてくるのですが、それを純粋に楽しめるかどうかというと、スタンスは色々ではないでしょうか。
邪神なんて、見たら発狂するに決まってる、太刀打ちできるわけがないんだから、なんとか封印したり時間稼ぎしたりしよう!とか、茫然自失のSAN値直葬だったりするはずですが、世の中にはそんなシナリオばかりではありません。
どちらかというと「立ち向かえるよ!核兵器なら大丈夫!だって核だから!ATフィールドだってN2爆雷程度でどうにかなるんだから!」などと、人類の叡智があれば圧倒的火力で退ける事は出来ると考えている人達もいるし、そういうシナリオが求められている場面も多い気がします。
ToCでは上記どちらにも対応出来るようにモードが2つ用意されていて、純粋に邪神に勝つ事など出来ないモードが純粋主義。マンガのように打ち勝つ事も可能とするモードがパルプとなっています。
必ずそのモードで遊べという事ではなく、それぞれ選択ルールが異なっていて純粋主義で遊びたい場合とパルプで遊びたい場合でルールが変わるだけで、詳しくは決めなくても大丈夫です。
ルールブック上ではそれがどちらかわかるように、アイコンがついています。一見してあまりわかりやすいアイコンではないので注意です。

読みやすくない部分も
CoCのルールブックを開いた時、読みづらいという印象は強く、ルールを難解に見せていると思います(パラノイアのルールブックはさらに上を行っている難解な表記だと思っています)
ToCではどうかというと、CoCと比較すればまだ読みづらくない程度、しかし、一般的なTRPGのルールブックと比べると見劣りするレベルです。
日本産では一番ポピュラーなTRPGシステムであるソードワールドを作ったグループSNEなのに、何故同じレベルで読みやすい本を作れないのか不思議です。
先に紹介した2つのモードを区別するアイコンも、どっちがどっちなのかいまいち掴みにくく、印がついている物とついていない物が混在して載っていたりします。例えば、職業選択時の一覧や掲載順は五十音順で記載されていて、わかりにくくなっています。
技能も大ジャンルである探索技能と一般技能の分別だけされており、その後は単なる五十音順でイラッとします。が、キャラクターシートでは探索技能の中でも技術系や科学系などで分けて記載されています(なら両方ともそれでいいのでは?)
CoCも基本的に五十音順で書かれているので、慣れた人にとっては良いかもしれませんが……個人的に、この書き方はあまり良いと思いません。
ただ、技能のカギカッコについて日本語版では<一般技能名>や《探索技能名》となっていて、おそらく原書よりは読みやすくされた部分もあります。
クトゥルフやニャルラトホテプなどの有名な邪神、旧支配者などは五十音順ですが、これは優劣を決定的にしない為、妥当だと思います。
さらに言うと、邪神にはステータスがなく、攻撃してもどうしようもない存在となっています。戦う以外の方法でどうするのかはシナリオによって決まるでしょう。

キャラ作成の概要
具体的な数値や方法の記載は避けますが、以下の手順で作られていきます。
- 職業の決定(職業技能の決定)
- 動機の決定
- 技能の購入
職業と動機
職業では、シナリオが始まるまでについていた職業が決められます。職業を決めると職業技能が自動的に割り振られ、後で技能を購入する時に値を伸ばしやすくなります。
CoCより種類が多いので、選ぶだけでも楽しめます。
動機は、キャラクターとクトゥルー神話(ToCでは「クトゥルー」に統一されている)との関わり方を決めます。例えば「好奇心」や「退屈」といった性格、人格に近い物を決めます。
順序はどちらでも大丈夫だと思うので、自分がキャラクターを作る時は、動機が先かな?と思っています。
技能の購入
技能の購入では、作成にあたって初期ポイントをもらって《探索技能》に割り振れます。割り振りたい技能が職業技能の場合、割安になります。《探索技能》に割り振れるポイントには限度があり、プレイヤーの人数に応じて変化しており、プレイヤーの人数が少ないほど、多く割り振れるようになっています。
いくつかの技能には、特別なルールがついていて、そもそも取得不可だったり、他の技能とセットで使用するポイントを決めたりする場合もあります。
どのくらい割り振った方がいいのかヒントも載っているので、ここは親切です。
CoCにはない技能で面白そうなのが《官僚制度》や《警官言葉》<嫌な気配>などでしょうか。キャラクターシートは公開されているので、どんな技能があるのかはルールブックを購入しなくても名前だけならわかります。
ポイントの割り振りが終わったら、後は名前などの設定を固めるくらいなので、キャラクター作成自体はそこまで時間がかからないようになっています。
不思議ですが、ToCでのキャラ作成のフローはルールブックに載っていませんから、それぞれのページをよく読んで作る必要があります。
全体的なルールの難しさ
CoC同様に細かいシチュエーションに対してルールがついているので、ガチガチにルールどおりにやろうと思ったら、キーパーになる人は読み込んでおく必要あります。
技能についても、特別な設定を持つ技能があるのでキーパーだけは把握しておくべきでしょう。
船長はその場の裁量でだいたい決めるので、あんまりルールにこだわらないですが……細かいシチュエーションにいちいちルールが決められているのは、若干窮屈かな?と感じます。

プレイヤーとして遊ぶなら、それほど詳しく読んだ状態でいる必要はありません。キーパーに言われた時、必要なだけ参照すれば良いのです。
とりあえず知っておくと楽なのは《探索技能》を持っていればその技能の判定で失敗する事がないのと<一般技能>は今までどおり失敗がありえるというくらいでしょうか。
細かくルールはありますが、基本のルールはその場で聞いてもすぐに出来るような内容が多いので、肝心なのは「どこにそのルールが載っているのか」を参照出来るように目次と索引を上手く活用出来るようになっておくと良いでしょう。
設定資料として
CoCのルールブックは設定資料としての側面もかなり強く、ToCはその一面だけ見たら情報量としては負けます。ただ、読みやすさはToCの方が高いかな?
読む気が失せる情報量でドッサリ見せられる感覚は同じですが、ToCの方が少ないので気楽です。
時代や作品によって扱いが変わっている物ばかりなので同じ項目内でも異説が併記されていて、シナリオを作る人からすると助かる書き方です。
シナリオ作成する人に向けて
現時点では1920年代のシナリオが作れるようになっています。データも全てその時代になっているので、現代の日本で遊びたい場合はシステムに載っていないデータを使用する事になります。
これって結構、遊びにくいって思う人いるんじゃないかな……と思うです。しかし、クトゥルフ神話を題材にしているのだから、まずは1920-30年代でやらなきゃね?と思うのと、そもそもガムシュー・システムは汎用RPGシステムだからキーパーの努力次第でなんとでもなると思うのです。
今はなくとも、クトゥルフ神話という題材そもそも人気のシリーズなので、サポートも充実するかも?という期待もしつつ、それが整うまではテキトーにデータを流用して作っていいのではないかと思うのです。

今後の展開に期待
ああだこうだと、良い所も気になった所も媚びる事なく書きましたが、今後の展開に期待しているから!と思っていただければと思います。
単なる翻訳で終わらず、遊ぶ人が読みやすく、使いやすい物を出してもらえると嬉しいです。ゲームマスタリー・マガジンではサポートしてくれるらしいので、そちらは読みやすいのではないかと思っております。
ちなみに、ゲームマスタリー・マガジン14号にはToCに使えるデータがたくさん載ったマスタースクリーンがついてくるそうですよ。

ゲームマスタリーマガジン第14号posted with AmaQuick at 2021.01.30安田 均(著)
書苑新社 (2020-12-25T00:00:01Z)![]()
¥1,980 Amazon.co.jpで詳細を見る
Twitterで検索!
おまけ
「クトゥルフ」と読んでるの日本だけだそうです。
世界的には「クトゥルー」がスタンダードなので、春麗を「しゅんれい」と読むのをやめる時期があったように、いずれはクトゥルーで統一されるんでしょうかね?
ToCではCoCと表記が若干違う同じ者が色々。ガタノトーアはガタノソア、クトゥグアはクトゥガ、イスはイィス……どれかに統一して欲しい。
関係ないけど「スマートフォン」なのに略すと「スマホ」っていうのも気になってる。

暗黒神話TRPGトレイル・オブ・クトゥルーposted with AmaQuick at 2021.01.30ケネス・ハイト(著)
書苑新社 (2020-12-25T00:00:01Z)![]()
¥4,950 Amazon.co.jpで詳細を見る